当記事のリンクには広告が含まれています
ISO9001・IATF16949 第6章 計画
ISO9001 及び IATF16949 の第6章 は、以下の通りです。
(下表の ”要求事項” の部分をクリックすると、解説ページにいけます。 )
| 規格 | 項目 | 要求事項 |
| ISO9001:2015 | 6 | 計画 |
| ISO9001:2015 | 6.1 | リスク及び機会への取り組み |
| IATF16949:2016 | 6.1.2.1 | リスク分析 |
| IATF16949:2016 | 6.1.2.2 | 予防処置 |
| IATF16949:2016 | 6.1.2.3 | 緊急事態対応計画 |
| ISO9001:2015 | 6.2 | 品質目標及びそれを達成するための計画策定 |
| IATF16949:2016 | 6.2.2.1 | 品質目標及びそれを達成するための計画策定 – 補足 |
| ISO9001:2015 | 6.3 | 変更の計画 |
第6章の計画では組織のトップマネジメント(経営者)は品質方針を達成するにあたって、組織全体の計画を立てる段階についての要求事項が書かれています。
6.1.2.1 リスク分析

当該項目の、IATF16949要求事項のポイントを自分なりにまとめてみました。
・製品のリコールから学んだ過去の教訓
・製品監査
・市場で起きた回収、修理、苦情
・スクラップ及び手直しを
これらのリスク分析の結果は、文書化して保持しなければならない。
用語の解説
リスク分析
リスク分析とは、一般的にリスクアセスメントの一貫のことをいいます。リスクアセスメントは、リスクを特定し、分析(特性を理解したり、レベル検討したり)をし、評価(分析結果を基準と比較する)する一連のことです。
品質に関わるリスクは広範囲に及びますが、品質マネジメントシステムでは製品を作り上げるプロセス(製品実現プロセス)に関わるリスクを示しています。
具体的にいうと、IATF16949の要求事項に明記はされていませんが、FMEAを使うように要求しています。なお、FMEAはIATF16949の運用を支える『5つのコアツール』の1つです。

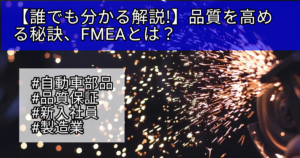
リコール
リコールは比較的、一般用語かもしれませんが大切な言葉になるので解説します。
お車をお持ちの方なら、想像がつくかもしれませんが、自動車において重要な品質問題が発生した場合、エンドユーザーに「ディーラーへ来てください」と依頼がくるかと思います。ディーラーへ自動車を持って行くと、無償で不具合対策製品を取付けてくれ、より安全に自動車を使うことができます。
このことを一般的にはリコールと呼びます。
リコールでは、不具合が起こらない対策品を増産したり、ディーラーでの部品脱着費用など、多大なロスコストを発生させます。ロスコストのみで済めば良いですが、人命に関わる不具合であれば、自動車メーカーや自動部品メーカーの信頼を大きく損失させる問題へつながります。
製品監査
こちらはIATF16949特有の用語になります。製品監査は、製品の品質特性を監査を行うことを示しています。
ここでいう品質特性とは、製品の品質を構成する要素であり、例えばネジでは、長さや固さ、ネジ穴の形状などが挙げられます。製品は完成形ではなく、「生産及び引き渡しの適切な段階で」監査することが要求されており、単に仕上がった製品の寸法を確認すれば良いわけではありません。
(ネジの製造に詳しくないですが…)
例えば、FMEAを使い、仕上がりの固さに素材を溶かす時間が影響することが判明したとすると、その溶かす時間の基準が定められていて、適切な帳票類で現場に指示がかかっているかどうかまで監査を行い、完成品の検査で固さチェックをする。
といった具合です。
はじめに
ISO9001の題6章「計画」について簡単に説明します。
簡単に言ってしまうと、その名の通り組織が品質方針を達成するうえでの、計画を立てる段階でやらなくてはならない内容が書かれています。
例えば、組織には年次計画があり、その中で監査計画を立てたりしていますよね。監査は不具合品を作る可能性(リスク)がないよう、正しくものづくりができているか確認する仕事です。
ISO9001ではリスクを特定し、しっかり管理するよう計画を立てることが要求されていますが、これでは高品質が求められる自動車部品においては不足していると考えられ、IATF16949にて追加された形になっています。
解説
既に用語の解説にも記載してしまいましたが、IATF16949では暗黙の了解として、リスク分析にはFMEAというツールを使うことが要求されています。その他にもリスク分析の代表として、FTAという分析手法もあります。
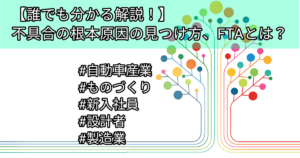
IATF16949では、リコールを意識した “不具合の予防” への対応の一つとして、リスク分析の内容が規定されています。
組織は最低限、ここの『リコールから学んだ教訓~手直し』までの内容を含めたリスク分析を行う必要があります。組織の製品にもよりますが、NG判定された製品でも手直しをして品質が保証できるのであればOK品として出荷をしているメーカーもあります。
例えば、部品の半田付けを手直しや、微小なシミやキズの手直しなどが挙げられます。
この“手直し”をする作業においても、FMEAでしっかりとリスク分析を行い、手直しをしたせいで余計な不具合(2次不具合)を起こさないようにするための要求事項となります。
なお、これらのリスク分析の結果は、文書化して保管をしておく必要があります。
ここで注意するポイントは、要求事項では、『保持』と似た意味で『維持』という言葉が良くでてきます。保持は、しっかり文書を管理し持っておくことに対して、維持は、文書を適宜更新をしていくという意味になります。例えば、出荷検査表などの事実が記載されている記録は『保持』しますが、組織表やFMEAなど随時アップデートが必要な文書は『維持』する必要があります。

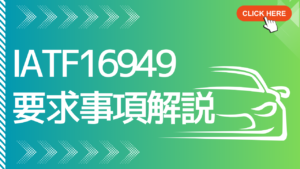

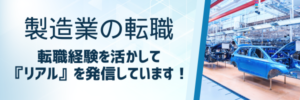

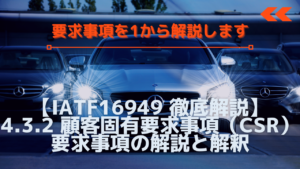
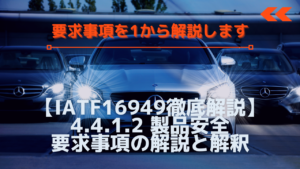
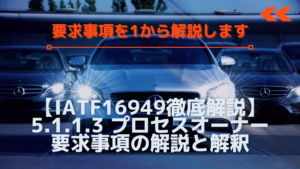
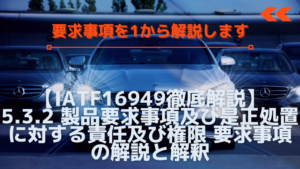
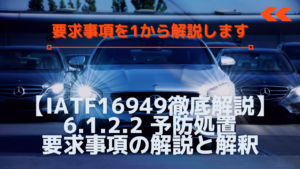

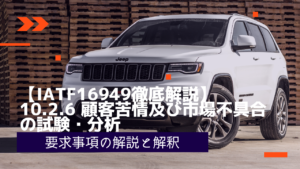

コメント